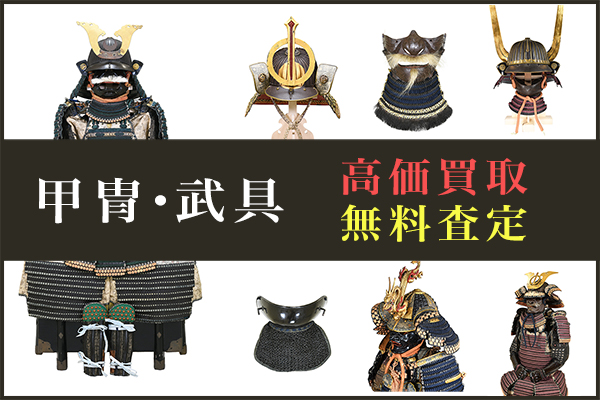日本刀の形態研究(七)-三
日本刀の形態研究 第四章 日本刀の発展について
第一節 古備前時代(古刀前期)-二
○古備前時代の作風
現存する作品によって古備前時代の作風を概括的に観察する時最も注意すべきは、今日に残し伝えられた作品は数多の研磨の結果を経ているものであるという事です。「古い刀は研ぎ減っている」という事を一応念頭に入れて観察しなくてはなりません。殊に造り込みは研磨の影響著しいものですから単純に「身巾やさしく帽子つまる」なんてやってはなりません。
造り込み=刃長は多く二尺六七寸、中には三尺に達するものもあります。反高くして鎬巾広い、帽子は原型俗に言う猪首帽子であったと思われます。
刃長二尺六七寸は今日残る生茎作品から見てそのように判断できます。鎬巾は広かったと思われ従って刀の身巾は相当にあったと考えなくてはなりません。
反りの高い事は常時刀剣が切るという点に主要目的をかけたためかと思われます。また刀身全体が極めて洗練されているのは茎の仕立ての原始的素朴さに比べて対照的ですが、それは後世研磨の手腕による近代化と見て差し支えないでしょう。原型にあっては茎も刀身も等しく幾分粗雑であったと考えてよいと思います。その様にして猪首帽子と言われるものが非技巧的であり古い時代日本刀の原型であって、今日我々が極めて普通に考えている孤状の美しい線を描いた帽子は後世の磨きのかかったものとしなくてはなりません。
刃文=古備前時代の刃文は多く小乱沸付です。これは何も備前物のみの特徴ではなく備中青江にしても同時代に当たる作者は類似の刃文です。これは地鉄と焼刃界が沸崩れて直刃の界を沸えしめた如き紋様をなしています。時代古いもの又は技術の拙いものは、所々沸が地鉄中に飛放たれ所々皆焼風をなし、或いは部分的に沸崩れ、焼落刃の交るものがある事です。これら全て一定の焼巾を保ちて刃鋼を形成するいう事からすれば非技術的でして、後世新刀などに於けるが如く意識してなしたものではありません。高熱による焼土の脱落から偶然地鉄中に焼きが入ったものです。常時においては刃文を作るのではなく、刃鋼を造る事こそ目的だったのですから、部分的な焼土脱落など問題ではなかったに相違ありません。しかし度重なり技術進歩し、習練を積むに至ればかかる土落などの失敗もなく一定の焼き巾が保たれるものと思われます。こうして完全な直小乱の作品となるのです。なお技術進む者はこれからして更に進んで直足入りにまで至っています。正恒、安綱の後期作品、有綱の如きにこの例をみます。
地鉄=鍛錬の回数は少なく、板目肌大きく、心鉄は用いず無垢鍛え。地鉄の精美は用鉄の材料その他によるもので、鍛錬の念入りと否とに関係するものではありません。この点古備前の板目肌は鍛錬の結果自然に現われたもので、後世の如く意識して作ったものではなく、刃文の小乱の場合と同様です。
茎=生ぶ茎に於いて古備前作品を観ますと茎全体の仕立ては極めて無雑作です。鎬筋も直線をなさず、面は凸凹著しいものさえ見受けます。鑢目も最も自然な筋違いで、又センスキのままのもあります。茎尻も後世の如く丁寧には作られておらず栗尻類似のものが大多数です。目釘穴は打抜きのままのもありロクロを用いてあけたものもあります。銘字は稚拙ともいうべき大きい二字銘が大部分を占めています。「備前國友成」「備前國包平」などの如く国名を入れたものがあっても飾り気なき素朴な書風は極めて風趣あるものとなっています。刀銘の習慣は大事令の制によるとされていますが、恐らく古い時代には作者銘を入れるという習慣はなかったのではと思われます。それは刀剣は古くは柄を外す事があまりなかったと考えられるからです。しかし日本刀の発生が武士階級と共にあったとすれば、刀工の銘切りの習慣も武士社会の名を重んずる精神と相応して行われたかと思われます。これよりして柄を外す必要がたとえなかったにしても茎のみ粗雑に作るという事は考えられないので、常時にあっては茎、刀身共々割合素朴な方法において製作されたと考えて差し支えないと思います。刀身は今日手を加えられて形を変えているが、茎の状態より刀剣の全体を察して誤りは無いでしょう。
注意=茎の一種に稚子股というのがあり古備前作品の様な古いものにあるとされています。これは茎尻が棟の方へ反り刃棟の部分が一部磨取られたものですが、刀工がこの形に茎を作ったのではなく後世外装の都合にて手を加えたものだと思います。
(日本刀要覧より。)